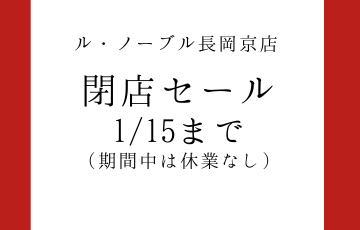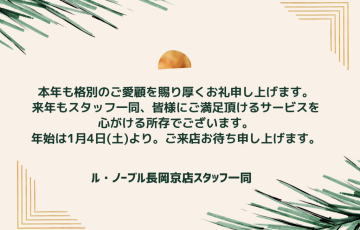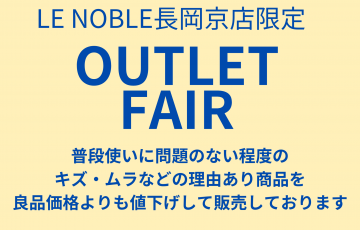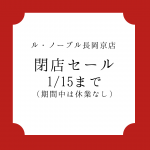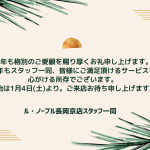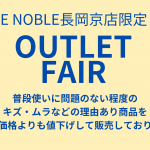【薩摩切子】
江戸末期に薩摩藩で造られた切子ガラスです。
鉛を24~25%含むクリスタルガラスを使用し、無色のガラス(クリアガラス)の表面に色ガラスを1~2mm程度溶着させた ”色被せガラス”にカットを施し、磨きあげた製品を「薩摩切子」と言います。
薩摩切子は、被せた色ガラスに厚みがありますが、色調が淡いためクリアガラスから色ガラスの間にできる グラデーション「ぼかし」が特徴です。

薩摩藩10代藩主 島津斉興が1846年に製薬館を創設し、医薬品の製造に着手。
江戸より硝子師、四本亀次郎を招き、化学薬品の薬瓶を製造し始めたのが発端です。
そして、1851年 島津斉彬が薩摩藩11代藩主に就任したことを機に、ガラス製造の目的が色被せ切子を作り出すことに変わり、海外の交易も視野に入れた美術工芸品「薩摩切子」が誕生。
その後ガラスの製造は切子という技法と共に盛大を極めましたが、斉彬の急逝により縮小、更に1863年 薩英戦争にてガラス工場も灰燼に帰しました。
その後、ガラス製造の再開や明治初期までガラス工場が存続していたと考えられる記述も残されていますが、明治10年(1877年)の西南戦争前後に薩摩切子の製造は途絶えたと思われます。

伝統の技と現代の技が生み出す薩摩の美「伝匠 薩摩切子」。
幕末から明治初頭に栄えた薩摩切子を、先人より伝えられた意匠と技術を受け継いだ匠が、現代の技術と発想を以って蘇らせました。
是非店頭で手にとって、歴史の重みと細やかな美しさを感じて下さい。
ただ今店内ファイナルサマーSALEも開催中です。

ご来店お待ちしております。
※ ご覧の時期によって価格等ご案内の情報が異なる場合がございます。最新の情報は各店舗にてご確認ください。